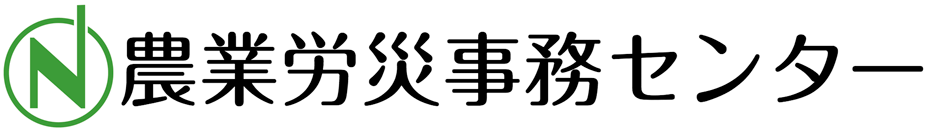労災保険の特別加入制度
先に特別加入についてご説明している、こちらをお読みいただくとさらに理解が深まります。
特定農作業従事者の特別加入が認められたのは、平成3年のことです。静岡のミカン農家さんが高所作業で労災保険に加入できないため、国に働き掛けて実現した、という経緯があるといわれています。
なので、指定農業機械作業従事者よりも補償範囲が広く定められていて、5つの特定農作業で事故に遭ったときに保険給付が認められます。
▶指定農業機械作業従事者を詳しく解説した記事はこちら
5つの特定農作業は下記の通りです。
一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業(以下「耕作等作業」)であって、次のいずれかに該当するもの
(1)動力により駆動される機械を使用する作業
(2)高さが二メートル以上の箇所における作業
(3)労働安全衛生法施行令別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4)農薬の散布の作業
(5)牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
(6)(1)~(5)に直接附帯する行為
特定農作業従事者として加入が認められる者の範囲
そして、特定農作業従事者として加入が認められる者の範囲は、規模要件が定められていて、自営農業者であれば誰でも加入できる指定農業機械作業従事者とは異なります。
① 年間農業生産物総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上の農業(畜産および養蚕を含みます)の事業場における耕作等作業
② 「事業場」については、一農家単位としますが、農家の集団が共同で行う場合(いわゆる地域営農集団または農事組合法人をいいます)は、当該集団を一つの事業場として取り扱いますので、個々の農家の規模が小さくても、営農集団または農事組合法人において、①の規模要件を満たせば、各構成農家につき規模要件を満たしたものとして取り扱います。
③ 農業生産物総販売額のうちには、農作業の受託料金は含まれません。また経営耕地面積には、田、畑、果樹園、牧草地および休耕地は含まれますが、作業受託の対象となる農地は含まれません。したがって、営農集団の構成員を除いて、作業受託のみにより農作業を行う者は特別加入の対象とはなりません。この場合、指定農業機械作業従事者か、特定フリーランスの特別加入をご検討ください。
④ 営農集団である、という判断は以下のとおりとされています。
ア 代表者および構成員の定めがあり、定款や規約等が整備されていること。
イ 共同作業の方法その他の集団内の作業に関する定めがあること。
ウ 経営所得安定対策等実施要綱に定める「集落営農」については、営農集団と認められます。
ということで、特定農作業従事者に加入する際は、規模要件を証明する書面の添付を求められます。
個人であれば、JAの証明書、市場の証明書、所得税の申告書その他年間農業生産物総販売額を証明できる書類、面積要件として農業委員会の証明書がいいでしょう。
集落営農であれば、定款または規約、共同作業の定めを記載した書面、加入する構成員の名簿、経営所得安定対策等実施要綱に定める集落営農であることを証明する書面、個人で記載した総販売額や利用権設定された農地面積を証明する書類などです。
農事組合法人であれば、登記簿謄本、加入する構成員が法人の組合員であることを証明する書面の添付(農事組合法人は規模要件審査は不要です)が必要となります。
なお、個人の規模要件ではなく、営農集団や農事組合法人の規模要件で加入した場合、当該集団・法人以外の個人での農作業は労災支給の対象とはならないのでご注意ください。
なぜ規模要件が設定された?
ちなみに、なぜ、特定農作業従事者に規模要件が設定されたかというと、通達にはこう書かれています。
「特別加入の対象となるべき者は、労働者に準じて労災保険により保護するに値する者であることが原則であること、また、保険技術上(業務上外の認定等)の観点から、家庭生活と区別できる程度に独立した規模を有する事業場に従事していることが必要である。また、今回の特別加入の新設の目的の一つは、当該特定加入に係る事業に使用される労働者への労災保険の適用拡大にあることから、労働者を使用する可能性の大きい(一定)の規模において作業する者(当該事業場に係る農地の所有者又は賃借人及びその共同作業者に限る。)に加入対象を限ることとした。」
今でも、常時5人未満の個人農家さんで働く労働者は労災保険の加入が義務付けられておらず、労災事故が起こっても保険で補償されないケースがとても多いと想定されています。
なので、平成3年以降は特別加入している農業者が労働者を雇ったときは、労災保険の加入が義務付けられることになりました。また労働者を雇っている人が特別加入する場合、労働者を労災保険に加入させなかったら、特別加入することができません。
5つの特定農作業の要件
そして、特定農作業とされる5つの作業についても、細かく決められています。
①農作業場において動力機械を使用して行う耕作等作業

農作業場には、特別加入の対象となる事業場(ほ場、牧場、格納庫、農舎、畜舎、堆肥場・草刈り場・サイロ・むろ等の恒常的作業場等)のほか、他のほ場等を含み、主として家庭生活に用いる場所は除きます。また、ほ場、牧場、格納庫、農舎、畜舎、恒常的作業場および共同出荷施設の相互間の合理的経路は含みます。
動力機械は、機械による身体の傷害の危険性が高いので、対象としたものです。動力機械とは、動力(電動機、内燃機関等)により駆動される機会の総称をいい、現在の指定農業機械はすべて含まれます。
直接附帯する行為としては、例えば耕作等作業中または耕作等作業の前後において行う耕作等作業のための動力機械の点検・修理作業(日常行い得るものに限る)、農産物を共同出荷施設まで運ぶ集荷作業・出荷作業、動力機械をほ場相互間において運転もしくは運搬する作業、苗・農薬・堆肥等を共同育苗施設等とほ場との間でトラック等で運搬する作業が原則として該当します。
一方、例えば労働者をほ場までマイクロ・バス等で送迎する作業、畜舎・農舎の建築作業等は、原則として直接附帯する行為には該当しません。
②農作業場の高さが2メートル以上の箇所における耕作等作業

労働安全衛生規則に準じて2メートル以上と定められています。なお、40度以上の傾斜地については、水平面から2メートル以上の高さにあれば、対象となります。
高さが2メートル以上の畜舎・農舎の屋根の補修作業または雪下ろし作業は、当該補修作業等が他に委託するよりも農業を行う者が通常行うべきものであって農作業に密接不可分な場合に限り、業務遂行性が認められます。
③サイロ・むろ等の酸素欠乏危険場所における耕作等作業
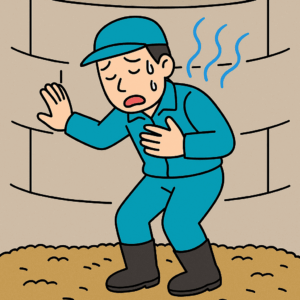
労働安全衛生法施行令で定められた場所とされ、穀物もしくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽またはキノコ類の栽培のために使用しているサイロ・むろ、倉庫、船倉、またはピットの内部です。
直接附帯する行為として、例えば家畜の飼育のための飼料の醗酵・貯蔵または土地の耕作のための堆肥の醗酵・貯蔵が、原則としてこれに該当します。
④農薬散布の作業

「農薬」とは農薬取締法第2条第1項に規定する薬剤であって、同法第3条各項の規定により登録を受けたものをいいます。
⑤牛・馬・豚に接触しまたはそのおそれのある耕作等作業

牛・馬は蹴られたり嚙まれたりする危険性が高く、豚は体重300キログラムにも及び、移送作業中の危険等が予測されるため対象となりました。ちなみに他の家畜の場合は、過去の例からみても、重大災害発生の可能性がないと見込まれています。
牛・馬・豚のいない畜舎内の清掃等の作業は含まれず、調教についても耕作等作業に該当しないので、対象とはなりません。直接附帯する行為としては、例えば家畜を一箇所に集めるため、檻等に追い込む作業が、原則としてこれに該当します。
厚生労働省からQ&A
なお、厚生労働省からQ&Aが出されていて、こちらの記事に詳しく掲載していますので、ご一読ください。